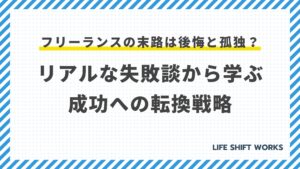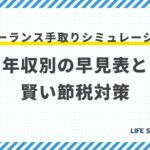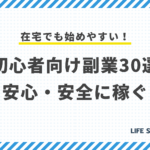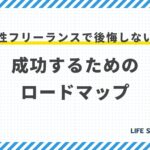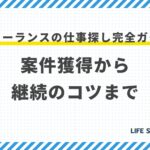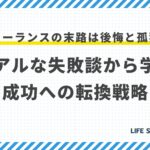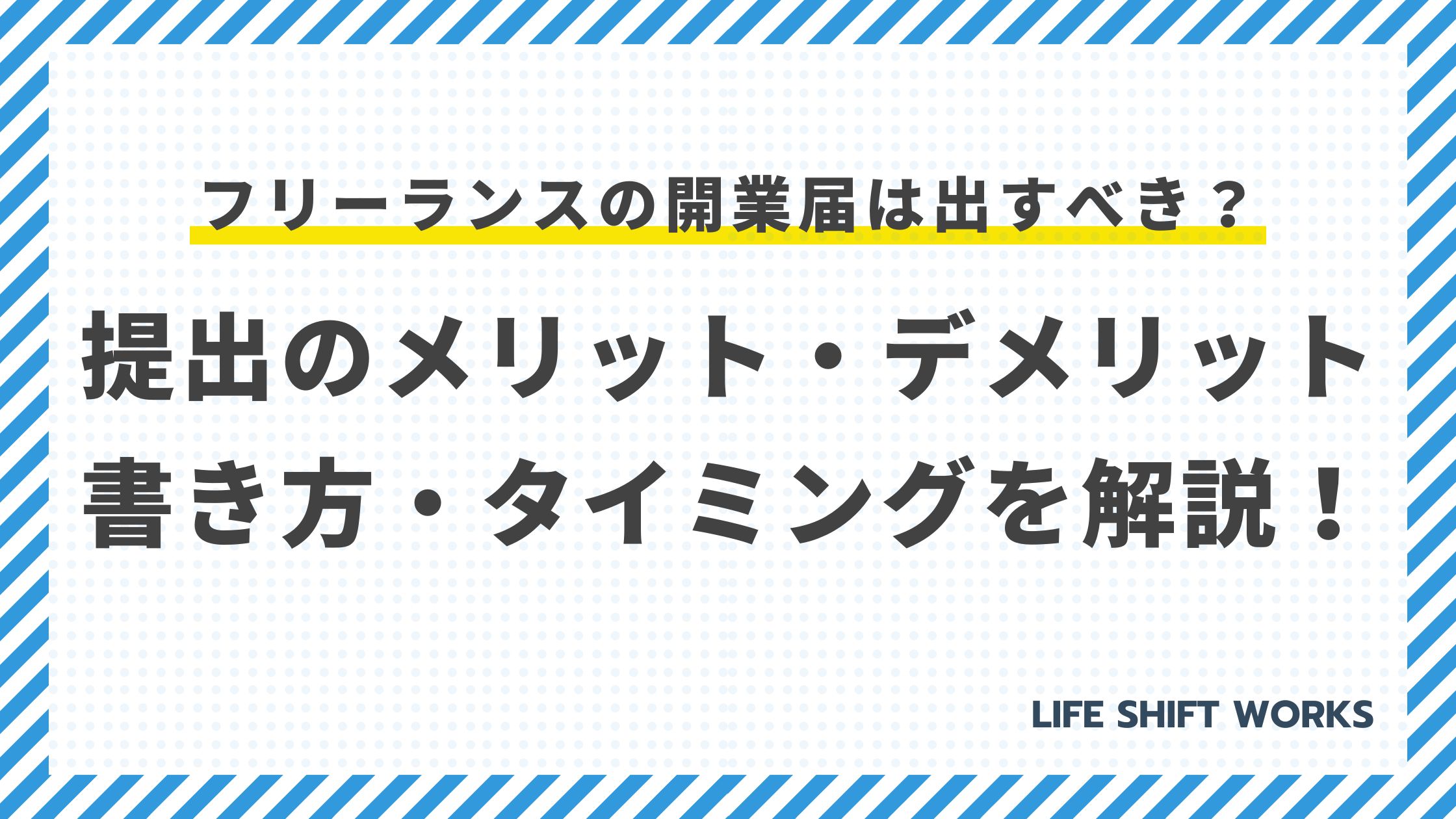
「フリーランスになったけど、開業届って出すべき?」「手続きがなんだか面倒くさそう…」「出さないと何か罰則があるのかな?」
会社を辞めて独立した方や、副業を本格的に始めたばかりの方は、このような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
税務署に書類を出すと聞くと、難しくて複雑なイメージを持つ人も多いでしょう。
しかし、開業届はフリーランスとしての活動を有利に進めるための、「お守り」のような存在です。
この記事では、開業届を出すべきか迷っているあなたのために、メリット・デメリットから具体的な書き方、提出後のアクションまで、専門用語を極力使わずに一つひとつ丁寧に解説します。
この記事を読み終える頃には、開業届への漠然とした不安は消え去っているはずです。
そして、自分にとって最適な選択をした上で、フリーランスとしての確かな一歩を踏み出せるでしょう。
Contents
そもそもフリーランスが出す「開業届」とは?
フリーランスとして活動を始めると、必ず耳にする「開業届」という言葉。
まず、この書類が一体何なのかを正しく理解することから始めましょう。
難しく考える必要はありません。
これは、あなたが事業を始めたことを国(税務署)に知らせるための、「事業開始の挨拶状」のようなものです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称
私たちが普段「開業届」と呼んでいる書類の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
これは所得税法という法律で、新たに事業を開始した個人が提出するよう定められています。
具体的には、以下のような所得が発生する事業を始めた場合に提出の対象となります。
- 事業所得:ライター、デザイナー、エンジニア、コンサルタントなど、多くのフリーランスが該当します。
- 不動産所得:アパート経営などで家賃収入がある場合です。
- 山林所得:山林を伐採したり、立木のまま売るなどして得た所得です。
この届出をすることで、あなたは税務署に「個人事業主」として認識されることになります。
「個人事業主」と「フリーランス」の違いは?
ここで、「フリーランス」と「個人事業主」という言葉の違いに戸惑う方もいるかもしれません。
この2つの言葉は同じ意味で使われることも多いですが、厳密には指すものが異なります。
| 用語 | 意味合い | 具体例 |
|---|---|---|
| フリーランス | 働き方を指す言葉 | 企業に属さず、案件ごとに契約を結んで仕事をする人 |
| 個人事業主 | 税法上の区分を指す言葉 | 税務署に開業届を提出して、事業を営む個人 |
つまり、フリーランスという働き方をしている人が税務署に開業届を提出することで、税法上「個人事業主」という立場になります。
開業届はいつまでに出す?提出義務と罰則の有無
「開業届って、いつまでに出さないといけないの?」
「もし出し忘れたら、罰則はある?」
これは、多くの人が抱く当然の疑問です。
結論から言うと、提出期限のルールはありますが、遅れたり提出しなかったりしても直接的な罰則はありません。
しかし、デメリットは存在します。
原則は事業開始から1ヶ月以内
所得税法では、開業届は「事業を開始した等の事実があった日から1ヶ月以内」に提出することと定められています。
では、「事業を開始した日」とは具体的にいつのことでしょうか。
これは一概には決まっておらず、自分で決めることができます。
- 店舗をオープンした日
- 初めてクライアントから仕事を受注した日
- 事業用の銀行口座を開設した日
- フリーランスとして活動すると決意した日
自分の状況に合わせて、客観的に説明できる日を開業日として設定しましょう。
提出が遅れても罰則はないが、青色申告に影響あり
開業届の提出が1ヶ月を過ぎてしまっても、罰金やペナルティはありません。
この点で、過度に心配する必要はないと言えます。
しかし、提出しないことによる最大のデメリットは、大きな節税効果のある「青色申告」のスタートが遅れることです。
- 青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
- この申請書は、原則として開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
- 開業届の提出が遅れると、この青色申告の申請も遅れてしまい、その年は節税メリットを受けられなくなります。
罰則がないからと後回しにすると、本来納める必要のなかった税金を納めることになりかねません。
収入いくらから出すべき?判断する3つのタイミング
「まだ収入が少ないけど、もう出すべき?」と悩む方も多いでしょう。
開業届を提出するのに、収入額の決まりはありません。
以下の3つのタイミングを目安に、自分の状況に合わせて判断するのがおすすめです。
1.事業所得が48万円を超えそうな時
フリーランスの所得(収入-経費)が年間48万円を超えると、確定申告の義務が発生します。
確定申告をするなら、節税メリットの大きい青色申告を選びたいところです。
そのため、所得が48万円に近づいてきたら、開業届の提出を検討しましょう。
2.青色申告で節税したいと思った時
収入の額にかかわらず、「節税したい」と思った時が開業届を出す絶好のタイミングです。
後述する最大65万円の控除を受けるためには、開業届と青色申告承認申請書の提出が必須です。
3.会社を辞めてフリーランスとして独立する時
本業としてフリーランス活動に専念するタイミングは、社会的なけじめとしても最適です。
ただし、失業保険の受給を考えている場合は、提出のタイミングに注意が必要です。
【損得比較】フリーランスが開業届を出す5つのメリット
開業届の提出は、単なる手続きではありません。
フリーランスとしての活動を有利に進め、手元に残るお金を増やすための強力な武器になります。
提出することで得られる5つの大きなメリットを具体的に見ていきましょう。
①【最大のメリット】青色申告で最大65万円の控除が受けられる
フリーランスにとって、開業届を出す最大のメリットは「青色申告」が可能になることです。
青色申告には、税金計算において非常に有利な特典がたくさんあります。
| 青色申告の主なメリット | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 所得から最大65万円を差し引ける。課税対象額が減り、税金が安くなる。 |
| 赤字の繰越し | 事業が赤字になった場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せる。 |
| 家族への給与を経費に | 生計を同一にする家族への給与を、経費として計上できる(要届出)。 |
所得税率を具体的に見てみましょう。
例えば、課税所得300万円の人の所得税率は10%です。
65万円の控除を受ければ、所得税で約6万5,000円、住民税と合わせると約13万円も手取りが増える計算になります。
②屋号付きの銀行口座が開設でき、社会的信用度が上がる
開業届を提出すると、「屋号」(お店や事務所の名前)を登録できます。
これにより、屋号付きの事業用銀行口座を開設できるようになります。
- 経理管理が楽になる:プライベートのお金と事業用のお金を明確に分けられ、確定申告の準備が楽になります。
- 取引先からの信頼度アップ:個人名義の口座よりも、屋号付きの口座の方が取引先に安心感を与え、信頼性が高まります。
③小規模企業共済に加入できる(フリーランスの退職金制度)
フリーランスには会社員のような退職金がありません。
そこで活用したいのが「小規模企業共済」です。
これは、国が運営するフリーランスや個人事業主のための退職金制度です。
- 毎月の掛金(1,000円~7万円)を積み立て、廃業時などに共済金を受け取れます。
- 掛金は全額が所得控除の対象となり、高い節税効果があります。
この制度に加入するには、原則として開業届の控えが必要になります。
④補助金や助成金の申請対象になる
国や地方自治体は、事業者を支援するための様々な補助金や助成金を用意しています。
これらの制度を利用する際、申請条件として「開業届を提出していること」が求められるケースが非常に多いです。
開業届は、あなたが公的に事業を営んでいることの証明書になります。
将来の事業拡大のチャンスを掴むためにも、提出しておくことが有利に働きます。
⑤事業用のクレジットカードや融資の審査に通りやすくなる
事業用の資金調達や経費管理においても、開業届は重要な役割を果たします。
- 事業用クレジットカード:開業届の控えを提出することで、審査に通りやすくなることがあります。
- 融資:日本政策金融公庫などから創業融資を受ける際、開業届は事業の実態を示す必須書類の一つです。
社会的信用が高まることで、事業運営の選択肢が広がります。
関連記事:フリーランス向けクレジットカードおすすめ14選!審査の不安を解消する5つの鉄則も解説
【要注意】開業届を出す前に知るべきデメリット・注意点3選
多くのメリットがある一方で、開業届の提出には慎重に検討すべき点もあります。
特に、会社員から独立する方や、配偶者の扶養に入っている方は注意が必要です。
後で「知らなかった」と後悔しないよう、3つのデメリットをしっかり確認しておきましょう。
①失業保険(失業手当)が原則もらえなくなる
会社を退職した後に受け取れる失業保険(雇用保険の基本手当)は、「失業状態」にある人の求職活動を支援するための制度です。
開業届を提出すると、あなたは「事業主」となり「失業状態ではない」と判断されます。
そのため、原則として失業保険を受け取ることができなくなります。
【対策】
- 会社を辞めてすぐに独立する場合、失業保険の給付をすべて受け終わってから開業届を提出しましょう。
- 開業の準備は受給中でも可能ですが、届出のタイミングには注意が必要です。
- 不明な点があれば、必ず管轄のハローワークに相談してください。
②配偶者の扶養から外れる可能性がある
配偶者の扶養に入っている方が開業届を出す場合、「扶養」には2種類あることを理解しておく必要があります。
| 扶養の種類 | 影響 | 判断基準の目安 |
|---|---|---|
| 税法上の扶養 | 配偶者の所得税・住民税 | あなたの合計所得金額が年間48万円以下。 |
| 社会保険上の扶養 | あなた自身の健康保険・年金 | 健康保険組合の規定による。収入が130万円未満など。 |
特に注意が必要なのは、「社会保険上の扶養」です。
加入している健康保険組合によっては、収入の有無にかかわらず、開業届を出した時点で扶養から外れるという規定を設けている場合があります。
扶養から外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料の負担が大きく増えます。
【対策】
- 開業届を提出する前に、必ず配偶者の勤務先へ連絡し、健康保険組合の規定を確認しましょう。
③【副業の場合】会社にバレるリスク対策が必要
副業としてフリーランス活動をしている会社員の方も注意が必要です。
開業届を提出したからといって、税務署から会社に通知がいくことはありません。
しかし、住民税の金額から副業が発覚する可能性があります。
【対策】
- 確定申告の際、住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。
- これにより、副業分の住民税の通知が自宅に届くようになり、会社に知られるリスクを大幅に低減できます。
関連記事:副業はなぜバレる?99%が知らない住民税の仕組みと会社にバレないための鉄壁対策5選
【状況別】あなたは出すべき?開業届提出の判断フローチャート
ここまで解説したメリットとデメリットを踏まえ、あなたが今、開業届を出すべきかどうかの判断を手助けするフローチャートを用意しました。
ご自身の状況に当てはめながら、順番にチェックしてみてください。
- 現在、失業保険を受給中ですか?
- はい → 受給が満了するまで提出は待つのがおすすめです。
- いいえ → 次の質問へ
- 配偶者などの社会保険の扶養に入っていますか?
- はい → 先に健康保険組合の規定を確認しましょう。開業届を出すと扶養から外れる場合は、保険料負担を考慮して慎重に判断してください。問題なければ次の質問へ。
- いいえ → 次の質問へ
- 大きな節税効果のある「青色申告」をしたいですか?
- はい → 今すぐ提出しましょう。青色申告承認申請書も一緒に提出するのがベストです。
- いいえ → 次の質問へ
- 屋号付き口座や小規模企業共済、補助金などに興味がありますか?
- はい → メリットを享受するために提出を検討しましょう。
- いいえ → 確定申告が必要になる所得(年間48万円超)が見込まれるまでは、急いで提出しなくても大きな問題はありません。
開業届の書き方を5ステップで徹底解説!
ここからは、いよいよ開業届の具体的な書き方を見ていきましょう。
実際の書類を前にすると難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫です。
一つひとつの項目を丁寧に解説するので、一緒に進めていきましょう。
ステップ1:開業届の入手と必要書類の準備
まず、手続きに必要なものを揃えましょう。
- 開業届の用紙
- 国税庁のウェブサイトからPDFをダウンロードして印刷できます。
- または、最寄りの税務署の窓口でもらえます。
- マイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード
- または、通知カード+運転免許証などの本人確認書類
- 印鑑(認印でOK)
ステップ2:基本情報の記入(提出先、納税地、氏名など)
書類の上半分は、あなたの基本情報を記入する欄です。
- 提出先:あなたの住所地を管轄する税務署名を記入します。国税庁のサイトで調べられます。
- 提出日:書類を提出する日付を記入します。
- 納税地:原則として「住所地」にチェックを入れ、住民票のある住所と電話番号を記入します。
- 氏名・生年月日・個人番号など:間違いのないように正確に記入し、押印します。
ステップ3:事業内容の記入(職業、屋号、事業の概要)
フリーランスの方が最も悩むのがこの部分かもしれません。
- 職業:具体的な仕事内容がわかるように記入します。(例:Webデザイナー、ITエンジニア、ライター)
- 屋号:お店の名前のようなものです。なければ空欄でも問題ありません。屋号があると銀行口座を屋号名義で開設できます。(例:〇〇デザイン、ABCライティング)
- 事業の概要:職業欄よりも少し具体的に記入します。(例:Webサイトのデザイン及び制作、ソフトウェアの設計・開発)
ステップ4:届出区分と所得の種類の選択
ここはほとんどの方が同じ選択になります。
- 届出の区分:「開業」にチェックを入れます。
- 所得の種類:フリーランスの事業収入は、通常「事業所得」に該当します。ここにチェックを入れましょう。
ステップ5:その他項目(青色申告、給与など)の記入
最後に、残りの項目を埋めていきます。
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:青色申告をする場合は、「青色申告承認申請書」の「有」にチェックを入れます。同時に提出するのがおすすめです。
- 事業の概要:先ほど記入した内容と同じで構いません。
- 給与等の支払の状況:従業員や家族を雇わない場合は、全て空欄のままでOKです。
これで開業届は完成です。
開業届の提出方法3選!あなたに合ったやり方は?
完成した開業届は、3 つの方法で提出できます。
あなたの都合に合わせて最適な方法を選びましょう。
| 提出方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 税務署の窓口 | その場で不備をチェックしてもらえる、控えをすぐにもらえる | 平日の日中に行く必要がある | 初めてで不安な方、確実に手続きを終えたい方 |
| 郵送 | 時間や場所を選ばずに提出できる | 控えの返送に時間がかかる、不備があるとやり取りが面倒 | 日中忙しい方、税務署が遠い方 |
| e-Tax(電子申請) | 自宅で 24 時間いつでも提出できる、ペーパーレス | マイナンバーカードやICカードリーダライタ等の準備が必要 | PC操作に慣れている方、手続きをオンラインで完結させたい方 |
【確実】税務署の窓口に直接持参する
最も確実で安心な方法です。
職員の方がその場で内容を確認してくれるので、記入ミスがあっても訂正できます。
提出用の書類と同じ内容を記入した「控え」も必ず持参し、受付印(収受印)を押してもらいましょう。
この控えが公的な証明書になります。
【手軽】郵送で提出する
税務署に行く時間がない方におすすめです。
提出用の開業届と控えの2部に加え、「切手を貼った返信用封筒」を同封するのを忘れないようにしましょう。
この返信用封筒で、受付印が押された控えが返送されます。
【便利】e-Tax(オンライン)で電子申請する
自宅のパソコンからオンラインで手続きを完結できる方法です。
マイナンバーカードと、それを読み取るICカードリーダライタ(または対応スマホ)があれば利用できます。
提出したデータや受付完了通知が、控えの代わりになります。
【2025年〜】開業届の控え(収受印)が廃止に?証明が必要な時の対処法
ここで一つ、重要な法改正の情報をお伝えします。
2025年1月から、税務署の窓口や郵送で提出した際の「受付印(収受印)」が原則として廃止されます。
「では、どうやって提出したことを証明するの?」と不安になりますが、ご安心ください。
屋号付き口座の開設などで提出証明が必要な場合は、以下の方法で対応できます。
- 窓口・郵送の場合:提出前に、自分で開業届のコピーを取っておく。
- e-Tax の場合:申請後の受付完了通知(メッセージボックスに届く)を印刷または保存しておく。
これらが、従来の受付印付きの控えと同等の証明書類として扱われます。
節税効果を最大化!開業届と一緒に出すべき重要書類
開業届を提出するなら、節税効果を最大限に引き出すために、以下の書類も一緒に提出することを強くおすすめします。
これらはあなたの手元に残るお金を大きく左右する重要な書類です。
必須!「所得税の青色申告承認申請書」
青色申告のメリットを享受するためには、この書類の提出が不可欠です。
提出期限は、原則として開業日から 2 ヶ月以内です。
忘れてしまうと、その年は白色申告しかできなくなってしまうため、開業届と同時に提出するのが最も確実です。
【インボイス対応】「適格請求書発行事業者の登録申請書」
2023 年 10 月に始まったインボイス制度に対応するための書類です。
クライアントが法人や課税事業者の場合、あなたからの請求書がインボイスでないと、クライアントが税金面で不利になることがあります。
取引先との関係を考慮し、開業のタイミングで登録を検討しましょう。
【該当者のみ】家族に給与を払う場合などの届出
もし、配偶者や親族を従業員として雇い、給与を支払う場合は、以下の書類も必要です。
- 青色事業専従者給与に関する届出書:家族への給与を経費にするために必要です。
- 給与支払事務所等の開設届出書:初めて従業員を雇う場合に提出します。
開業届を提出した後にやるべきことリスト
開業届の提出はゴールではなく、スタートです。
フリーランスとして事業を円滑に進めるために、以下の手続きも忘れずに行いましょう。
国民年金・国民健康保険への切り替え手続き
会社を退職して独立した場合、厚生年金や会社の健康保険から脱退することになります。
退職日の翌日から 14 日以内に、お住まいの市区町村役場で国民年金と国民健康保険への加入手続きが必要です。
事業用銀行口座の開設とクレジットカードの準備
プライベートのお金と事業のお金をきっちり分けることは、正確な経理の第一歩です。
開業届の控えを使って、屋号付きの事業用銀行口座を開設しましょう。
経費の支払いを事業用のクレジットカードにまとめると、管理がさらに楽になります。
会計ソフトの導入と日々の帳簿づけ
青色申告(特に 65 万円控除)を行うには、複式簿記という正規のルールで日々の取引を記録(記帳)する必要があります。
これを手作業で行うのは非常に大変です。
freee やマネーフォワード クラウドといったクラウド会計ソフトを導入すれば、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動で取り込めます。
簿記の知識がなくても、ガイドに従うだけで簡単に帳簿が作成でき、確定申告の手間を大幅に削減できます。
フリーランスの開業届に関するよくある質問(FAQ)
最後に、多くの方が抱く細かい疑問について、Q&A 形式でお答えします。
Q. 開業届の提出に費用はかかりますか?
いいえ、開業届の提出自体に手数料は一切かかりません。
無料で手続きできます。
Q. 副業の場合、会社にバレることはありますか?
開業届を提出したことが、税務署から直接会社に通知されることはありません。
ただし、副業の所得が増えると住民税の額が変わり、会社の給与から天引きされる際に経理担当者に知られる可能性があります。
対策として、確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、副業分の住民税の通知が自宅に届くようになり、会社に知られるリスクを低減できます。
Q. 開業日や屋号を後から変更できますか?
はい、変更できます。
開業日や屋号を変更するための特別な届出は、基本的に必要ありません。
ただし、屋号を変更した場合は、銀行口座の名義変更など、関連する手続きを忘れずに行いましょう。
まとめ:開業届はフリーランスとしての第一歩!賢く活用して事業を加速させよう
この記事では、フリーランスの開業届について、その必要性から書き方、提出後のアクションまでを網羅的に解説しました。
開業届の提出は、単なる面倒な手続きではありません。
それは、あなたの事業を公的に認めさせ、青色申告という強力な節税策をはじめとする多くのメリットを享受するための「権利」を手に入れるための重要なステップです。
この手続きを自分自身でやり遂げる経験は、フリーランスとしての自覚と自信を深めてくれるはずです。
この記事を参考に、賢く制度を活用し、あなたの事業を力強く加速させてください。
あなたの新たな挑戦を心から応援しています。
▼ 【個人事業主/フリーランス向け】知っておきたい法務や税務
▼ フリーランスのための案件獲得方法
| フリーランスが登録すべき案件サイト一覧 | フリーランスエージェントとは? |
| フリーランスの仕事探し完全ガイド | フリーランスエージェント面談完全ガイド |
| フリーランスエージェント活用術 |