記事監修とは?E-E-A-T対策で効果を最大化!費用相場から依頼方法まで徹底解説
-
- 最終更新日時
- 2025.10.17
-
- 作成日時
- 2025.10.17
-
SEO対策
-
- 著者
- SIDER STORY 編集者
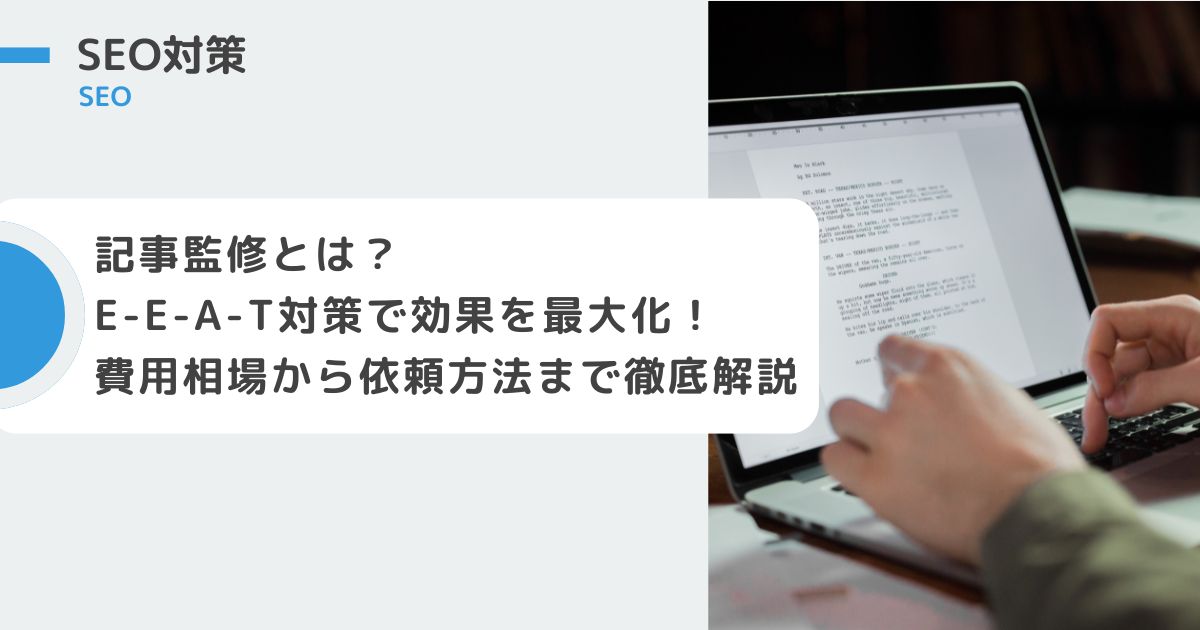
専門性の高いコンテンツでSEO評価を上げたいけれど、どうすれば良いか分からない。
多くのWeb担当者が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。
その有効な解決策が「専門家による記事監修」です。
しかし、その具体的な効果や進め方、費用については不明な点も多いはずです。
この記事では、記事監修の基本からSEOへの影響、具体的な依頼手順までを網羅的に解説します。
読み終える頃には、監修導入を社内で自信を持って提案できるようになるでしょう。
記事監修とは?SEOにおける重要性とE-E-A-Tとの関係
なぜ今、多くのメディアで記事監修が注目されているのでしょうか。
それは、Googleの評価基準が変化し、コンテンツの「質」がより厳しく問われるようになったからです。
特に、読者の人生に大きく関わる専門的な情報では、その信頼性が検索順位を左右します。
ここでは記事監修の基本と、SEO評価の核となる「E-E-A-T」との深い関係を解き明かします。
記事監修の定義と2つの依頼パターン
記事監修とは、専門家が記事の内容をチェックし、その品質を保証することです。
情報の正確性や信頼性を高める目的で行われます。
依頼方法には、大きく分けて2つのパターンがあります。
自社のリソースや予算に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 記事監修 | 専門的な知見を持つ第三者が、記事内容の正確性・信頼性・網羅性を確認し、品質を保証すること。 |
| パターン | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 1. 記事制作後に監修のみ依頼 | ライターが作成した記事を専門家が確認する | ・コストを抑えやすい ・進行がスピーディ | ・専門家の意図と異なると大幅な修正が必要 ・情報の深掘りが限定的になる場合がある |
| 2. 執筆から監修まで一貫依頼 | 専門家自身が記事を執筆し、内容を保証する | ・非常に高品質で独自性の高い記事になる ・修正の手間が少ない | ・コストが高くなる傾向がある ・専門家のスケジュール確保が必要 |
Googleが重視する「E-E-A-T」と監修の役割
E-E-A-Tとは、Googleがコンテンツの品質を評価するための重要な指標です。
良質なコンテンツの条件として、Googleは以下の4つを挙げています。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| E-E-A-T | Googleの検索品質評価ガイドラインで示される、Webサイトやコンテンツの評価基準。Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthinessの頭文字。 |
- Experience(経験):コンテンツの作成者が、そのテーマについて実際に経験しているか。
- Expertise(専門性):コンテンツの作成者が、そのテーマについて専門的な知識やスキルを持っているか。
- Authoritativeness(権威性):コンテンツの作成者やWebサイトが、その分野の権威として広く認知されているか。
- Trustworthiness(信頼性):コンテンツの情報が正確で、読者が安心して信頼できるか。
記事監修は、このE-E-A-Tを直接的に高めるための、極めて有効な手段です。
専門家の知見は「専門性」を、その経歴や実績は「権威性」を担保します。
第三者による客観的なチェックは、記事全体の「信頼性」を大きく向上させるのです。
記事監修がもたらすSEOとビジネスへの5大メリット
記事監修は、単に検索順位を上げるためだけのものではありません。
読者からの信頼獲得やブランドイメージ向上に繋がり、最終的な事業成果に貢献します。
ここでは、監修を導入することで得られる具体的なメリットを5つ紹介します。
SEOとビジネス、両方の側面からその価値を理解していきましょう。
①【SEO効果】専門性・権威性・信頼性が向上し、検索順位上昇に貢献
記事監修がもたらす最も直接的なメリットは、E-E-A-Tの向上によるSEO評価の向上です。
Googleは「誰がその情報を発信しているか」を非常に重視しています。
特に、金融や医療、法律といったYMYL領域では専門性が不可欠です。
専門家による情報の裏付けは、上位表示の可能性を高める重要な要素の一つと言えるでしょう。
- 専門家の知見により、情報の正確性と網羅性が高まる
- 監修者のプロフィールを掲載することで、権威性と信頼性をGoogleに伝えられる
- 結果として、検索エンジンからの評価が高まり、検索順位の上昇が期待できる
②【顧客体験】情報の正確性が担保され、ユーザー満足度とコンバージョン率が向上
優れたコンテンツは、検索エンジンだけでなく読者のためにも作られるべきです。
専門家のお墨付きがあることで、ユーザーは安心して記事を読み進めることができます。
この信頼感が、サイト全体の顧客体験を向上させます。
結果として、ビジネス上の成果にも繋がる好循環が生まれるのです。
- ユーザーは安心して情報を得られ、満足度が高まる
- サイトの滞在時間が長くなり、離脱率が低下する
- コンテンツへの信頼が、商品やサービスへの信頼に繋がり、問い合わせや購入を後押しする
③【権威性】監修者の知名度による被リンクやサイテーション(言及)獲得
業界で著名な専門家に監修を依頼できた場合、思わぬ副次効果が期待できます。
監修記事が、監修者自身のWebサイトや関連機関から紹介される可能性があるからです。
このような外部からの言及は、質の高い被リンクやサイテーションとなります。
これらはサイト全体のSEO評価を高める、強力な要因になるのです。
④【ブランド価値】炎上リスクの低減と企業・サービスの信頼性向上
Webでの情報発信には、常に「炎上」のリスクが伴います。
特に専門的な分野で誤った情報を発信すれば、企業の信頼は大きく損なわれます。
記事監修は、専門家の目で事前に内容をチェックするプロセスです。
事実誤認や不適切な表現を防ぐ「防波堤」として機能します。
これは企業のブランドイメージを守る、重要なリスク管理と言えるでしょう。
依頼前に知っておきたいデメリットと注意点
記事監修には多くのメリットがありますが、実行する上での注意点も存在します。
良い面だけでなく、デメリットも事前に把握しておくことが成功の鍵です。
ここで挙げる課題を理解し、対策を準備しておきましょう。
コスト(費用・時間)とコミュニケーションの課題
専門家に依頼するため、当然ながら費用が発生します。
監修費用に加えて、社内の担当者がやり取りに費やす工数も考慮すべきです。
監修者との円滑なコミュニケーションも重要になります。
修正の意図を正確に汲み取り、フィードバックを反映させるための体制が必要です。
監修者選定を誤るリスクと回避策
監修者選びは、施策の成否を分ける最も重要な要素です。
専門分野が記事のテーマと少しでもずれていると、的確な監修は期待できません。
Webコンテンツへの理解が乏しい専門家を選んでしまうケースもあります。
その場合、修正のやり取りが煩雑になる可能性があります。
適切な監修者を見極める慎重な選定プロセスが不可欠です。
【5ステップで解説】記事監修の依頼から公開までの全手順
実際に記事監修を進めるには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。
ここでは、依頼から記事公開までの5つのステップを解説します。
この手順に沿って進めれば、担当者も迷うことなくプロジェクトを進行できるはずです。
STEP1:監修の目的と依頼範囲の明確化
まず、なぜ監修を行うのか、その目的を明確にしましょう。
SEO評価の向上なのか、ブランドの信頼性担保なのかで、依頼内容も変わってきます。
次に、監修者にどこまでお願いするか、依頼範囲を具体的に定義します。
依頼範囲を事前に固めておくことで、後の費用交渉や進行がスムーズになります。
依頼範囲の例
- 事実確認(ファクトチェック)のみ
- 表現の調整や専門用語の言い換え
- 不足している情報の追記提案
- 記事構成の提案から執筆まで
STEP2:監修者の選定と比較(依頼文テンプレート付)
次に、記事のテーマに最適な専門家を探します。
探し方には、以下のような方法があります。
| 探し方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 専門家紹介サービス | 質の高い専門家を効率的に探せる | 仲介手数料が発生する場合がある |
| 人脈・知人の紹介 | 信頼関係を築きやすい | 適切な専門家が見つかるとは限らない |
| SNSやWebで直接打診 | 直接交渉できる | 返信がない場合や条件交渉が難しいことがある |
依頼する際は、丁寧かつ明確な依頼文が重要です。
以下のテンプレートを参考に、自社の状況に合わせて調整してください。
依頼文テンプレート
件名:【株式会社〇〇】記事監修のご依頼(専門分野:△△)
〇〇様
突然のご連絡失礼いたします。
株式会社〇〇でメディア「△△」の編集を担当しております、〇〇と申します。
この度、〇〇様のWebサイト(またはご著書など)を拝見し、
△△の分野における深いご知見に感銘を受け、ご連絡いたしました。
現在、弊社メディアで「(記事のテーマ)」に関する記事を企画しており、
ぜひ〇〇様に監修をお願いできないかと考えております。
つきましては、一度オンラインにて、本件の詳細やご条件について
お話しさせていただくお時間を頂戴できないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
STEP3:監修の実施とフィードバック対応
監修者との契約が完了したら、記事の原文や資料を共有して監修を依頼します。
監修者からは、修正指示やコメントといった形でフィードバックが返ってきます。
修正意図が不明な点は必ず確認し、認識の齟齬がないようにしましょう。
編集方針と異なる指摘があった場合は、その背景を丁寧に説明し、相談しながら進めます。
円滑なコミュニケーションが、より良い記事を作るための鍵となります。
STEP4:監修者情報の準備と掲載
記事の信頼性を読者と検索エンジンに示すため、監修者のプロフィールを準備します。
事前に、掲載可能な情報の範囲(顔写真の有無、経歴の詳細度など)を確認しておきましょう。
快く情報を提供してもらえるよう、掲載イメージを事前に共有するとスムーズです。
掲載するプロフィールは、読者からの信頼を得られるよう、丁寧な紹介文を心がけます。
記事監修の費用相場は?料金体系とコストを抑えるコツ
記事監修を検討する上で、最も気になるのが費用ではないでしょうか。
費用は、監修者の実績や依頼範囲によって大きく変動します。
社内で予算を確保するためにも、料金の相場感を把握しておきましょう。
依頼パターン別の料金相場(文字単価/記事単価)
料金体系は、文字数に基づく「文字単価」や記事単位の「記事単価」が一般的です。
依頼範囲が広くなるほど、料金は高くなる傾向にあります。
| 依頼範囲 | 料金相場の目安 |
|---|---|
| ファクトチェックのみ | 1文字 1〜3円 / 1記事 1〜3万円 |
| リライト・追記含む監修 | 1文字 3〜8円 / 1記事 3〜8万円 |
| 新規執筆+監修 | 1文字 5円〜 / 1記事 5〜15万円以上 |
※上記はあくまで目安です。専門分野の難易度や監修者の知名度によって変動します。
費用対効果を高める3つのポイント
コストを最適化し、費用対効果を高めるためにはいくつかのコツがあります。
単に安さを求めるのではなく、質の高い監修を適正価格で依頼することを目指しましょう。
1.依頼範囲を明確に絞る
全ての記事に監修を入れるのではなく、特に専門性が求められる重要記事に絞る。
2.複数記事をまとめて依頼する
単発ではなく、複数記事をまとめて発注することで、単価交渉がしやすくなる場合がある。
3.長期的なパートナーシップを築く
継続的に依頼することで、監修者との信頼関係が深まり、柔軟な対応や価格交渉が期待できる。
【差がつく】監修者情報の最適な見せ方|SEO効果を高める3つのポイント
監修者プロフィールは、単に掲載すれば良いというものではありません。
見せ方を工夫することで、SEO効果をさらに高め、競合サイトと差をつけることができます。
ここでは、より一歩進んだ具体的なテクニックを3つ紹介します。
① 必須項目と読者の信頼を得るプロフィールの書き方
読者と検索エンジンの両方から信頼されるプロフィールには、含めるべき項目があります。
以下の情報を網羅し、監修者の専門性や人柄が伝わるように紹介しましょう。
プロフィールの必須項目
- 顔写真
- 氏名、ふりがな
- 肩書、所属(〇〇大学教授、〇〇クリニック院長など)
- 保有資格
- 簡潔な経歴と実績
- 公式サイトやSNSへのリンク
② 監修者紹介ページの作成と内部リンク戦略
より効果的な方法として、監修者一人ひとりの詳細な紹介ページを作成することが挙げられます。
そのページには、詳しい経歴や実績、監修した記事の一覧などを掲載します。
そして、各監修記事からこの紹介ページへ内部リンクを設置します。
この構造により、サイト全体の専門性と権威性がGoogleに伝わりやすくなり、SEO評価の向上が期待できます。
③ 【上級者向け】構造化データ(reviewedBy)の実装でGoogleにアピール
構造化データとは、検索エンジンがページの内容を正確に理解するための情報です。
reviewedByというプロパティを使用し、監修者情報をコードとして記述します。
これにより「この記事は、この専門家によって監修されています」という情報を、Googleに直接伝えられます。
専門的な知識が必要ですが、検索結果で特別な表示(リッチリザルト)に繋がる可能性があります。
まとめ:記事監修は高品質コンテンツへの投資。信頼されるメディアを目指そう
この記事では、記事監修の定義からSEO効果、具体的な進め方までを解説しました。
記事監修は、コンテンツの品質を飛躍的に高めるための重要な施策です。
それは単なるコストではなく、読者からの信頼を獲得し、メディアの価値を高める「未来への投資」です。
まずは自社メディアの中で、どの記事から監修を導入すべきか検討することから始めてみてはいかがでしょうか。
監修者紹介 Profile

大学在学中に株式会社デジタルトレンズに入社
- 自社メディア事業として複数メディアを統括し、社内MVPを複数回受賞。
- 新規事業部を立ち上げ、広告・SEOを含む複数施策のプロジェクトを1人で完結。
- 新卒1年目から福岡支社長に抜擢され、0からの立ち上げを経験。
2023年に独立し、株式会社サイダーストーリーを創業
- Webマーケティングを駆使した受託事業・自社事業を展開。
- AIを活用した業務効率化/業務標準化にも挑戦中。
