【2025年】Webマーケティングとは?施策の全体像から外注先の選び方まで解説
-
- 最終更新日時
- 2025.09.22
-
- 作成日時
- 2025.09.17
-
Webマーケティング
-
- 著者
- SIDER STORY 編集者
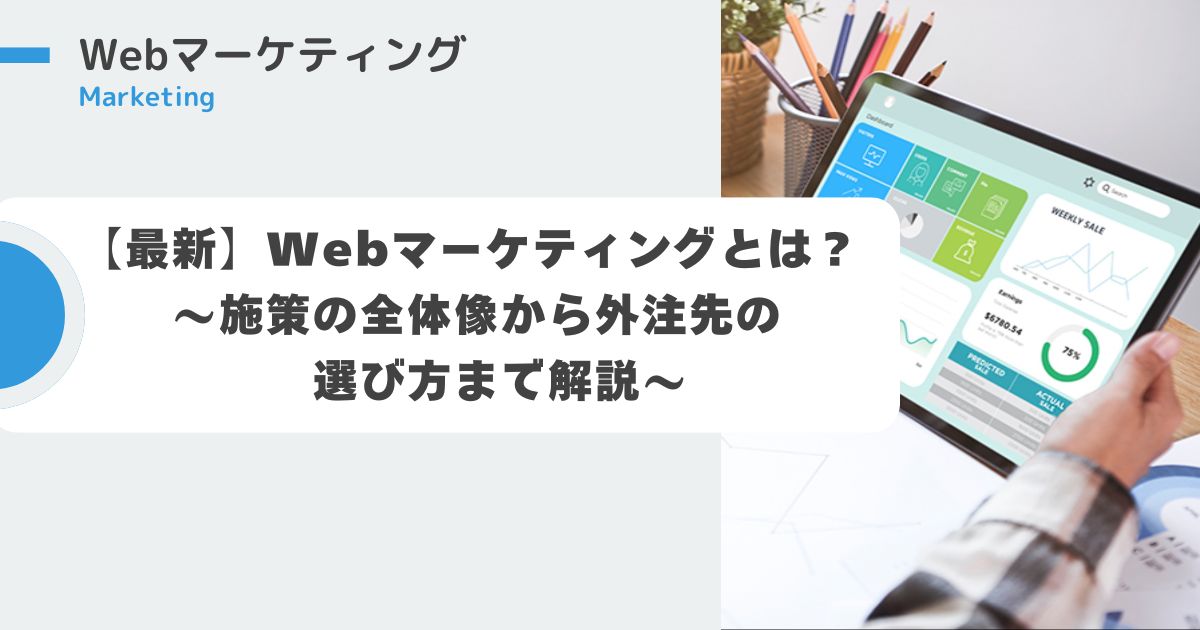
「社内でWebマーケティングの重要性が高まっているけれど、何から手をつければいいのだろう…」
「外部の専門家にお願いするのも一つの手だけど、どうやって選べばいいかわからない…」
こうした課題は、多くのマーケティング担当者の方が一度は抱える、共通の悩みではないでしょうか。
この記事では、Webマーケティングの基本的な定義から、具体的な施策の全体像、そして成果を出すための戦略の立て方まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事が単なる施策の紹介で終わらないのは、Webマーケティングを「フロー型」「ストック型」「コミュニティ型」という3つのモデルで捉え、あなたの会社が今どの戦略に力を入れるべきか、その判断軸を具体的にお伝えする点にあります。
読み終える頃には、「次に何をすべきか」が明確になり、自信を持って内製か外注かの判断、そして最適なパートナー選びまでできるようになっているはずです。
Webマーケティングとは?経営層も納得させる重要性と定義
Webマーケティングを社内で推進するには、まず「なぜ必要なのか」を関係者、特に経営層に理解してもらうことが大切ですよね。
ここでは、その第一歩となるWebマーケティングの定義と重要性について、基本から解説します。
Webマーケティングの定義をわかりやすく解説
Webマーケティングとは、ひと言でいうと「インターネットを使って、自分たちの商品やサービスが自然と売れていく仕組みをつくること」です。
実は、私たちが普段何気なく目にしたり、利用したりしているものの多くが、このWebマーケティング活動の結果なのです。
身近なWebマーケティングの例
- SNSの広告で見かけた洋服が気になって、ついクリックして買ってしまった。
- 「近くのカフェ」と検索して、一番上に出てきたお店に足を運んでみた。
- 好きなインフルエンサーが紹介していたコスメを、試しに購入してみた。
これらはすべて、企業がWebサイトやSNS、広告、メールといったあらゆる接点を活用して、お客様に自社を知ってもらい、関係性を築いていくための活動です。
デジタルマーケティングとの関係性
Webマーケティングとよく似た言葉に「デジタルマーケティング」があります。
この二つの違いを理解しておくと、戦略を考える上で視野がぐっと広がります。
| 用語 | 領域 | 具体例 |
|---|---|---|
| デジタルマーケティング | デジタル技術を活用する全てのマーケティング活動 | Webサイト、SNS、スマホアプリ、デジタル広告、MA、IoTデータ活用、デジタルサイネージ |
| Webマーケティング | デジタルマーケティングの一部(Webサイトが中心) | SEO、Web広告、コンテンツマーケティング、メールマーケティング |
つまり、デジタルマーケティングという大きな傘の中に、Webマーケティングが含まれている、というイメージです。
なぜ今、Webマーケティングが事業成長に欠かせないのか?
現代において、Webマーケティングはもはや「やってもやらなくてもいい選択肢」ではなく、事業成長に「不可欠な取り組み」となりつつあります。
その背景には、私たちの購買行動の大きな変化があります。
- 情報収集の変化: かつて主流だったテレビや雑誌に代わり、WebサイトやSNSが主な情報源になりました。
- 比較検討の変化: 口コミサイトを見れば、実際に使った人のリアルな声を簡単に知ることができます。
- 購買場所の変化: お店に行かなくても、ECサイトでいつでもどこでも買い物ができるようになりました。
こうした変化の中で、企業がWeb上でお客様との接点を持つことは、事業を成長させる上で欠かせない活動となっているのです。
従来のマーケティングとの違い
担当者としてWebマーケティングの予算を取る際に、テレビCMのような従来型のマーケティングとどう違うのか、説明を求められる場面は少なくないでしょう。
Webマーケティングの大きな強みは、その「科学的なアプローチ」にあります。
| 比較項目 | Webマーケティング | 従来のマーケティング(例: テレビCM) |
|---|---|---|
| 費用 | 低コストから始められる | 高額な費用がかかる |
| 効果測定 | アクセス数など、詳細なデータで測定可能 | 効果測定が難しい(視聴率など間接的) |
| ターゲット | 年齢や興味関心で細かく設定できる | 幅広い層に届くが、絞り込みは困難 |
| 改善 | データを見ながらリアルタイムで改善可能 | 一度放映すると修正が難しい |
データという客観的な事実に基づいて、費用対効果を正確に測り、改善を重ねていける。
これこそが、Webマーケティングが事業成長の力強いエンジンとなり得る最大の理由です。
【戦略モデルで理解】Webマーケティングの全体像と3つの型
Webマーケティングにはたくさんの施策がありますが、それらを闇雲に始めてしまうのは避けたいところです。
ここでは、あなたの会社の目的や状況に合わせて戦略を立てるための3つの考え方(モデル)をご紹介します。
あなたの会社はどれ?目的別で考える3つの戦略モデル(フロー/ストック/コミュニティ)
Webマーケティングの施策は、その性質から大きく「フロー型」「ストック型」「コミュニティ型」の3つに分けることができます。
このフレームワークを使うことで、自社の課題解決にどの施策がフィットするのかが見えやすくなります。
| 戦略モデル | 特徴 | 目的 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| フロー型 | 短期集客モデル。「蛇口」のように、投資すればすぐに集客できるが、止めると流れも止まる。 | 短期的な売上向上、キャンペーン告知、即時的なリード獲得 | ・即効性が高い ・効果測定が容易 | ・広告費がかかり続ける ・資産になりにくい |
| ストック型 | 中長期資産モデル。「ダム」のように、時間と労力をかけて良質なコンテンツを蓄積し、継続的な集客を生み出す。 | 継続的なリード獲得、ブランディング、採用力強化 | ・一度構築すれば資産となる ・広告費を抑えられる | ・成果が出るまで時間がかかる ・専門知識が必要 |
| コミュニティ型 | 関係性構築モデル。顧客やファンとの対話を通じて、エンゲージメントを高め、LTV(顧客生涯価値)を最大化する。 | 顧客ロイヤリティ向上、ファン育成、ブランドイメージ向上 | ・顧客が自社のファンになる ・口コミ(UGC)が発生しやすい | ・丁寧なコミュニケーションが必要 ・成果が売上に直結しにくい |
この3つの戦略モデルについては、以下の動画で「蛇口とダム」という比喩を使いながら、より分かりやすく解説しています。
戦略の全体像を掴むために、ぜひ一度ご覧になってみてください。
3つのモデルと8つの主要施策のマッピング
では、具体的なマーケティング施策が、これら3つのモデルのどこに当てはまるのかを見ていきましょう。
それぞれの施策が持つ戦略的な役割を理解することが、とても重要です。
▼戦略モデルと主要施策のマッピング
- フロー型(短期的な流れ)
- Web広告
- アフィリエイト広告
- ストック型(中長期的な蓄積)
- SEO
- コンテンツマーケティング
- YouTube
- コミュニティ型(継続的な関係)
- SNSマーケティング
- メールマーケティング
- ウェビナー
多くの企業では、これらのモデルを単独で使うのではなく、うまく組み合わせています。
例えば、「フロー型のWeb広告で短期的に見込み顧客と出会い、ストック型のコンテンツでじっくりと関係を育て、コミュニティ型のSNSでファンになってもらう」といった、複合的な戦略がとても効果的です。
主要施策8つの詳細比較表(目的・メリット/デメリット・費用感)
それぞれの施策の特性を理解し、自社の戦略に最適な組み合わせを見つけるために、こちらの比較表も参考にしてみてください。
| 施策 | 主な目的 | メリット | デメリット | 費用感(月額) |
|---|---|---|---|---|
| SEO | 検索エンジンからの継続的な集客 | ・広告費が不要 ・資産性が高い ・ブランディング効果 | ・成果が出るまで時間がかかる ・アルゴリズム変動リスク | 30万円~100万円 |
| Web広告 | 即時的な集客、特定ターゲットへの訴求 | ・即効性が高い ・ターゲティング精度が高い | ・広告費がかかり続ける ・運用ノウハウが必要 | 20万円~数百万円 |
| SNSマーケティング | 認知拡大、ブランディング、ファン育成 | ・拡散力が高い ・ユーザーと直接交流できる | ・炎上リスクがある ・継続的な運用が必要 | 10万円~50万円 |
| コンテンツマーケティング | 見込み客の育成、専門性の提示 | ・潜在層にアプローチ可能 ・顧客との信頼関係構築 | ・コンテンツ制作コストがかかる ・成果まで時間がかかる | 30万円~100万円 |
| メールマーケティング | 見込み客・既存顧客へのアプローチ | ・低コストで実施可能 ・One to Oneのアプローチ | ・リストの質が重要 ・開封率の低下傾向 | 5万円~30万円 |
| アフィリエイト広告 | 成果報酬型の販売促進 | ・費用対効果が高い ・認知度を広げやすい | ・意図しない形で紹介されるリスク ・ブランドイメージ毀損リスク | 成果報酬 + 5万円~ |
| ウェビナー | リード獲得、見込み客の育成 | ・質の高いリードを獲得しやすい ・場所の制約がない | ・集客が必要 ・企画や運営の工数がかかる | 10万円~50万円 |
【施策別】Webマーケティングの具体的な手法と内製・外注のポイント
ここでは主要な4つの施策を取り上げ、自社でやるか(内製)、専門家に任せるか(外注)を判断する際のポイントを、よくある失敗例とあわせて見ていきましょう。
SEO(検索エンジン最適化)
SEOは、Googleなどの検索結果で、自社のサイトを上位に表示させるための施策です。
広告費をかけずに、多くの人に見てもらえるチャンスが生まれます。
- 内製する場合の注意点: 専門知識を持つ人材の確保や育成が不可欠で、常に最新情報を学び続ける姿勢が求められます。コンテンツ作りから技術的な改善まで、やるべきことも多岐にわたります。
- 外注する場合のメリット: 専門家が持つ最新のノウハウをすぐに活用でき、社内のリソースを本来の業務に集中させることができます。
- よくある失敗例: 目的とズレたキーワードで対策してしまうこと。検索数は多くても、自社のビジネスに繋がらないキーワードで上位表示されても、なかなか成果には結びつきません。
関連記事:SEOとは?SEO対策の基本と最初に行うべき具体施策15選
Web広告
費用をかけて、WebサイトやSNS上に広告を出す手法です。
SEOとは対照的に即効性があり、狙ったターゲット層に的確に情報を届けられるのが強みです。
- 内製する場合の注意点: 広告の管理画面は機能が多く複雑なため、使いこなすには慣れが必要です。日々の数値をチェックし、細かく調整していく地道な作業が成果を分けます。
- 代理店に依頼するメリット: 豊富な運用経験に基づいた最適な設定や改善案を提案してもらえます。最新の広告メニューに関する情報も得やすいでしょう。
- よくある失敗例: 代理店に丸投げしてしまい、成果が出ないこと。自社の強みやお客様の情報を代理店としっかり共有し、二人三脚で進める意識が大切です。
SNSマーケティング
InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などを活用する手法です。
一方的に情報を発信するだけでなく、ユーザーと直接コミュニケーションをとることで、親近感や共感を育んでいきます。
- 自社でやるべきこと: ブランドの世界観や「中の人」の個性を反映した日々の投稿や、ユーザーとの何気ないコミュニケーションは、内製で行う方が気持ちが伝わりやすいです。
- 外注できること: 戦略設計やキャンペーンの企画・実行、レポート分析など、専門性が求められる部分は外注を検討すると良いでしょう。
- よくある失敗例: 炎上リスクの管理ができていないこと。不適切な投稿一つで、ブランドイメージが大きく傷つく可能性があります。事前に社内で投稿のガイドラインを決めておくことが不可欠です。
コンテンツマーケティング
ブログ記事や動画などを通じて、ユーザーにとって価値ある情報を提供し続ける手法です。
すぐに商品を売り込むのではなく、まず信頼関係を築き、将来のファンになってもらうことを目指します。
- 内製する場合の注意点: 企画、執筆、編集、デザインなど、コンテンツ作りには様々なスキルが必要です。継続的に質の高いコンテンツを生み出す体制をどう作るかが鍵になります。
- 制作会社へ依頼する際のポイント: ただ文章が書けるだけでなく、SEOや事業全体への理解があるか、戦略から一緒に考えてくれるか、といった視点でパートナーを見極めることが重要です。
- よくある失敗例: 成果に繋がらないコンテンツをたくさん作ってしまうこと。「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」という戦略がないままでは、自己満足で終わってしまうかもしれません。
【5ステップ】Webマーケティング戦略の立て方と実践ロードマップ
成果の出るWebマーケティングは、場当たり的な施策ではなく、丁寧な戦略設計から始まります。
ここでは、外部のパートナーとプロジェクトを進めることを想定した5つのステップをご紹介します。
ステップ1:目的とKGI/KPIの目線合わせ
まず社内で決めること
- Webマーケティングで達成したい最終ゴール(KGI)は何か(例:売上〇〇円アップ)。
- その達成度を測るための中間目標(KPI)は何か(例:月間のお問い合わせ件数)。
パートナーと相談すること
設定したKGI/KPIが現実的か、より良い指標はないか、プロの視点からアドバイスをもらいましょう。
ステップ2:ターゲットとカスタマージャーニーの設計
まず社内で考えること
- 最も届けたいお客様はどんな人か(ペルソナ)。
- その人が商品を知ってから購入するまでの心の動きや行動(カスタマージャーニー)を想像しましょう。
パートナーと深めること
描いたペルソナやジャーニーについてフィードバックをもらい、市場データなども交えながら一緒に精度を高めていきます。
ステップ3:施策の優先順位と予算決定
まず社内で決めること
- 今回の取り組みにどれくらいの予算をかけられるかを明確にしておきます。
パートナーと相談すること
目標達成のために、どの戦略モデル(フロー/ストック/コミュニティ)にどれくらいの予算を配分するのが最適か。
短期・中期・長期の視点で実行計画を提案してもらいましょう。
ステップ4:役割分担と施策実行
まず社内で決めること
- プロジェクトの責任者や担当者を決め、必要な情報(製品情報など)をスムーズに提供できる体制を整えます。
パートナーと決めること
どちらが何を担当するのか、具体的な役割分担を明確にしておきましょう。
施策の実行や確認のフローも事前に合意しておくと安心です。
ステップ5:定例会での報告と次のアクション検討
社内から伝えておくこと
レポートで特にどの数字を見たいか、事前に伝えておくとスムーズです。
関係者も定例会に参加し、その場で意思決定できるのが理想です。
パートナーに求めること
施策の結果(事実)だけでなく、その結果から何が言えるのか(考察)、そして次に何をすべきか(改善アクション)をセットで報告してもらいましょう。
Webマーケティングの成功確率を上げる3つのポイント
色々な施策やツールがありますが、本質的に成功の確率を高めるポイントは、次の3つに集約されます。
これは、良いパートナー企業を見極める際の基準にもなります。
データに基づいて判断するクセをつける
Webマーケティングの最大の武器は、あらゆる活動をデータで「見える化」できることです。
- 見るべきデータの例: サイトへのアクセス数、各ページの閲覧数、コンバージョン率、広告のクリック率など
- パートナー評価の視点: 定期的に分かりやすいレポートをくれるか。データから課題を見つけ出し、具体的な改善案を提案してくれるか。
勘や経験だけに頼るのではなく、データという客観的な事実をもとに仮説と検証を繰り返していく。
それが、成功への一番の近道です。
常に「お客様視点」を忘れない
優れたマーケティングは、いつだって「お客様が主語」です。
お客様視点の問いかけ
- お客様は、本当にこの情報を知りたがっているだろうか?
- この広告は、お客様にとって有益だろうか、それとも邪魔だろうか?
- このサイトは、お客様が迷わず目的を達成できるだろうか?
パートナー評価の視点
- 企業の「売りたい」気持ちだけでなく、お客様のインサイトに基づいた提案をしてくれるか。
- ペルソナやカスタマージャーニーを深く理解しようとしてくれるか。
自分たちの都合を押し付けるのではなく、お客様に価値を提供した結果として選んでいただく、という姿勢が何よりも大切です。
最新トレンドを学び続ける(AI活用、プライバシー保護など)
Webマーケティングの世界は、技術の進歩やルールの変更によって、常に変化しています。
最新の重要トレンド
- AI活用: ChatGPTのような生成AIを使ったコンテンツ制作やデータ分析。
- プライバシー保護: Cookie規制強化に対応した、プライバシーに配慮したデータ計測。
- 動画コンテンツ: TikTokやYouTubeショートに代表される、短尺動画の活用。
パートナー評価の視点
- 最新の技術トレンドや市場の変化に詳しいか。
- 古い成功体験に縛られず、新しい挑戦を後押ししてくれるか。
変化に対応し、学び続ける姿勢こそが、継続的な成果を生み出す鍵となります。
【知らないと危険】Webマーケティング担当者が守るべき法律・ガイドライン
Webマーケティングは、便利な反面、意図せず法律に触れてしまうリスクも潜んでいます。
ここでは、担当者として最低限知っておきたい法律をご紹介します。
信頼できるパートナー企業かどうかを判断するリテラシーとしても役立ちます。
景品表示法(ステマ規制)
消費者に誤解を与えるような、不当な表示を禁止する法律です。
- 注意すべきポイント:
- 優良誤認表示: 事実以上に商品やサービスが優れているように見せかけること。
- 有利誤認表示: 価格などの取引条件が、実際よりもすごくお得であるかのように見せかけること。
- ステマ規制: 2023年10月から、広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング」が明確に禁止に。インフルエンサーに依頼する際は「#PR」などの明記が必須です。
特定電子メール法
受け取る人の同意なく、広告・宣伝目的のメールを送ることを規制する法律です。
- 注意すべきポイント:
- 原則として、事前に「送ってもいいですよ」と同意してくれた人にしか、広告宣伝メールは送れません(オプトイン方式)。
- メール本文には、送信者の名前や住所、そしていつでも配信停止できる案内(オプトアウト)を記載する義務があります。
個人情報保護法(Cookie規制関連)
個人情報の適切な取り扱いについて定めた法律です。
- 注意すべきポイント:
- Webサイトで個人情報を取得する際は、何に使うのかを明示し、本人の同意を得る必要があります。
- Cookie情報も、他の情報と組み合わせることで個人が特定できる場合は個人情報と見なされます。サイト訪問時に表示される「Cookie利用への同意」のバナーは、この法律に対応するためのものなのです。
失敗しないWebマーケティング代行会社の選び方と比較ポイント
良いパートナーと出会えるかどうかは、Webマーケティングの成否を大きく左右します。
ここでは、代行会社を比較検討する際にチェックすべき4つのポイントを解説します。
どこまでお願いできるか(業務範囲)を確認する
代行会社によって、得意なことや対応してくれる範囲は様々です。
確認すべきこと
- 戦略を立てるところから相談できるか。
- コンテンツや広告クリエイティブの制作といった実務も任せられるか。
- 施策実行後の分析や改善提案まで、一貫してサポートしてくれるか。
ポイント
まずは自社で「どこまでを自分たちでやって、どこからをプロに任せたいのか」を整理しておくことが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。
料金体系を比較する(固定費・成果報酬・複合型)
料金体系には、主に3つのタイプがあります。
| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 固定費型(リテイナー型) | 毎月決まった費用を支払う | ・予算管理がしやすい ・幅広い業務を依頼できる | ・成果が出なくても費用がかかる |
| 成果報酬型 | CV数など、成果に応じて費用が発生 | ・費用対効果がわかりやすい ・リスクを抑えやすい | ・成果の定義が曖昧だとトラブルに ・お願いできる施策が限られる |
| 複合型 | 固定費と成果報酬を組み合わせる | ・両方の良いところを取れる | ・料金体系が複雑になりやすい |
実績を確認する(自社の業界・規模に近い事例はあるか)
過去の実績は、その会社の力量を知るための分かりやすい指標です。
確認すべきこと
- 自社と同じ、あるいは近い業界での支援実績はあるか。
- 自社と同じくらいの事業規模の会社の支援経験はあるか。
- 具体的な数字を伴った成功事例を紹介してくれるか。
ポイント
業界特有の事情やお客様の気持ちを理解しているパートナーであれば、より的確な提案が期待できます。
担当者の専門性とコミュニケーションの相性を見極める
最終的にプロジェクトを動かすのは、やはり「人」です。
確認すべきこと
- 窓口となる担当者は、Webマーケティング全般に関する深い知識と経験を持っているか。
- レスポンスは速いか、報告は丁寧かなど、気持ちよくコミュニケーションできそうか。
- 自社のビジネスを理解しようという熱意を感じられるか。
ポイント
契約前の打ち合わせには、可能であれば、実際にプロジェクトを担当する予定の人に同席してもらうのがおすすめです。
Webマーケティングに関するよくある質問(FAQ)
Q1. Webマーケティングの費用相場はどれくらいですか?
A1. 費用は、お願いする施策の種類や規模によって本当に様々です。
中小企業の場合、月額30万円~100万円くらいが一般的なボリュームゾーンでしょうか。
例えば、Web広告の運用代行なら月額20万円~、SEOコンサルティングなら月額30万円~が一つの目安になります。
大切なのは、金額そのものよりも「その予算でどんな成果を目指すのか」を明確にすることです。
Q2. 成果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか?
A2. これも施策によって異なります。
Web広告のような「フロー型」の施策は、始めてから1ヶ月ほどで効果が見え始めることが多いです。
一方で、SEOやコンテンツマーケティングのような「ストック型」の施策は、効果を実感できるまでには、少なくとも半年~1年くらいは見ておきたいところです。
短期的な成果と、中長期的な資産づくりをバランス良く計画することが大切です。
Q3. BtoBとBtoCで、Webマーケティングの戦略は変わりますか?
A3. はい、大きく変わります。
BtoC(個人向け)は、比較的、感情やその場の勢いで購入が決まることも多いので、SNSでの共感や魅力的なビジュアルが効果的な場合があります。
一方、BtoB(企業向け)は、複数人で合理的に判断することが基本なので、製品の機能や導入事例、費用対効果などを論理的に伝えるコンテンツやウェビナーが重要になる傾向があります。
関連記事:ウェビナーツール15選:選び方から活用、成功の秘訣まで完全網羅!
Q4. 良い代行会社と悪い代行会社の見分け方を教えてください。
A4. 良い会社は、契約前にビジネスの状況や課題をじっくりヒアリングし、具体的な目標(KGI/KPI)を設定した上で、その達成に向けた戦略を提示してくれます。
成功事例だけでなく、過去の失敗談や考えられるリスクについても正直に話してくれる会社は、信頼できる可能性が高いです。
逆に、「必ず儲かる」「絶対に1位になれる」といった根拠のない言葉を並べたり、レポートの提出が遅い、質問への回答が曖昧だったりする会社には、少し注意が必要かもしれません。
まとめ:Webマーケティング成功の鍵は、最適な戦略とパートナー選び
この記事では、Webマーケティングの基本から、全体像を捉えるための3つの戦略モデル、そして実践的な戦略の立て方とパートナー選びのポイントまでを解説しました。
- Webマーケティングとは、Webを中心とした活動で事業の成果を最大化すること。
- 施策は「フロー型」「ストック型」「コミュニティ型」の3モデルで戦略的に考えるのがカギ。
- 成果を出すには、データに基づいた判断と、徹底したお客様視点が欠かせない。
- 成功の鍵は、自社の課題に合った戦略を描き、それを一緒に進めてくれる最高のパートナーを見つけること。
Webマーケティングは、もはや専門部署だけのものではありません。
事業の未来を支える、大切な経営戦略の一つです。
この記事が、あなたの会社がその第一歩を踏み出すための、ささやかな後押しとなれば幸いです。
もし、「自社に最適な戦略がわからない」「信頼できるパートナーを探している」といったお悩みがありましたら、ぜひ一度、私たちにお気軽にご相談ください。
あなたの会社の課題に合わせた、最適なプランをご提案します。
監修者紹介 Profile

大学在学中に株式会社デジタルトレンズに入社
- 自社メディア事業として複数メディアを統括し、社内MVPを複数回受賞。
- 新規事業部を立ち上げ、広告・SEOを含む複数施策のプロジェクトを1人で完結。
- 新卒1年目から福岡支社長に抜擢され、0からの立ち上げを経験。
2023年に独立し、株式会社サイダーストーリーを創業
- Webマーケティングを駆使した受託事業・自社事業を展開。
- AIを活用した業務効率化/業務標準化にも挑戦中。
